1716466811
2024-05-23 12:00:27
第二トーマス礁はスカボロー礁と並んで、中国とフィリピンの間の南シナ海紛争の主な発火点となっている。 これら 2 つの地理的特徴は、中国の戦略的取り組みの中心となっており、特に「グレーゾーン」活動への関与が特徴です。
これらのアクティビティの特徴は、 代理戦争戦術、中国海警局(CCG)や人民軍海上民兵などの組織によって行われた強制措置を通じて実証されました。 グレーゾーン戦術を展開することで、北京政府は2013年以来、南シナ海における戦略的地位を強化してきた。
しかし、中国政府による第二トーマス礁周辺の作戦努力の強化にもかかわらず、具体的な成果は依然として得られていない。 中国がグレーゾーン内で有効性の限界に達しているかどうかを検討する必要がある。
2013年、中国は南シナ海の領有権を主張し強化するため、大規模な埋め立て運動を開始した。 同時に、CCGは第2トーマス礁周辺の定期パトロールを開始し、その間、BRPシエラマドレのフィリピン軍前哨基地へのフィリピンの補給任務を妨害した。
第二次世界大戦時代のこの船は、1994 年に中国が近くのミスチーフ礁を占領したことへの対応として、1999 年に意図的に座礁させられました。その位置により、前哨基地では部隊のローテーションと重要な生命維持物資の補給が必要です。 散発的な事件にもかかわらず、状況は比較的安定していました。 まだ、 2022年以降中国海警局と人民武装海上民兵の活動は激化しており、浅瀬周辺ではますます攻撃的な戦術が展開されている。
フィリピンと中国の船舶間の最も重大な衝突 2023年に発生した, 重大事故が5件記録されています。 で 2023年2月、CCGの船舶は、ローテーションと補給任務を支援するフィリピンの船舶に軍用レベルのレーザーを配備しました。 で 8月、 11月 そして 12月、CCGは補給船に対して放水銃を使用した。 10月と12月にも船舶間の衝突が発生した。 危険な行動 CCGによって実行されました。
真ん中 海上事故の激化 第二トーマス礁周辺では、南シナ海の緊張が引き続き高まることが予想される。 2024 年第 1 四半期の出来事は、この傾向をさらに強調しています。 2024 年 3 月には、 2つの危険な状況 中国海警局が危険な行動を取り、放水砲を使用した結果、フィリピンの補給船の乗組員7人が軽傷を負った事件が起きた。
中国がグレーゾーン活動において積極的な措置を採用しているにもかかわらず、フィリピンの補給ミッションは 2023年に実施 2024年初頭の計画は成功した。北京は、セカンド・トーマス礁の制圧を容易にするシナリオであったBRPシエラマドレ基地から重要な物資を遮断するという目標を達成できなかった。これらの展開は、北京がフィリピンを武力紛争の閾値以下に抑止するための手段を使い果たしたことを示唆している。
中国のグレーゾーン活動を制限することの有効性は、2023年2月から始まる南シナ海における中国の強硬な行動を公表するというフィリピンの新たな戦術に関連している。
フィリピン政府による南シナ海における中国船舶の活動に関する体系的な記録と公表、およびメディアとの協力は、主権保護措置に対する国民の支持を強化した。
ミッション情報の一般公開は極めて重要です。 2021 年には、以前と比べてミッションの 43 パーセントのみが公開されました。 80パーセント 2023年。世論調査 2023年12月に フェルディナンド・マルコス・ジュニア政権の南シナ海紛争への対応を61パーセントが支持していることを示し、前四半期からの持続的な増加を反映している。
南シナ海紛争に関するフィリピンの透明性向上の取り組みも国際目標の推進につながり、中国への圧力を強めている。フィリピンが中国の圧力に遭遇したとの報告は、ますます国際的な注目を集めている。
2023年3月の補給任務に対する海警局の放水砲の使用は、 特別なステートメント 欧州連合および数カ国からの声明。これらの声明は、フィリピンへの連帯、緊張の高まりに対する懸念、中国の行動に対する非難を表明し、フィリピンの国際的な影響力を強化している。
セカンド・トーマス礁付近での中国の活動は、南シナ海の係争地域に対する支配力強化には成功していない。むしろ、北京のアプローチはフィリピン国民の中国に対する懐疑心を深めている。2024年の調査によると、中国か米国のどちらかと連携するよう強いられた場合、フィリピン人の大半は米国と連携すると答えている。
フィリピンは2年連続でASEAN加盟国の中で最も米国を支持する国として浮上した。 中国のフィリピンに対する持続的な攻撃的な行動と、中国政府が建設的な対話に参加したり、ホットラインなどの仕組みを通じて緊張を緩和したりすることに躊躇していることは、中国政府がフィリピン国民の支持低下を懸念していないことを示唆している。
フィリピンにおける反中感情の高まりは、北京のグレーゾーン戦術のもう一つの挫折とみなされるべきである。フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は、フィリピン軍を国内の脅威から国外の脅威へと方向転換した。マニラ 関係を強化した 米国との協力を強化し、日本やオーストラリアを含む地域の利害関係者との二国間関係を発展させてきました。また、フィリピン・日本・米国の三国間会合など、小規模な形式での協力も深めています。
フィリピンの立場は強化された。 中国政府が直接攻撃をエスカレートさせた場合、中国政府は1951年の米比相互防衛条約の発動と、他の地域大国、特にオーストラリアと日本の関与を検討する必要があるだろう。
マテウシュ・チャティスはウッチ大学アジア問題センターの上級専門家です。
#北京の南シナ海戦略の先行き不透明感


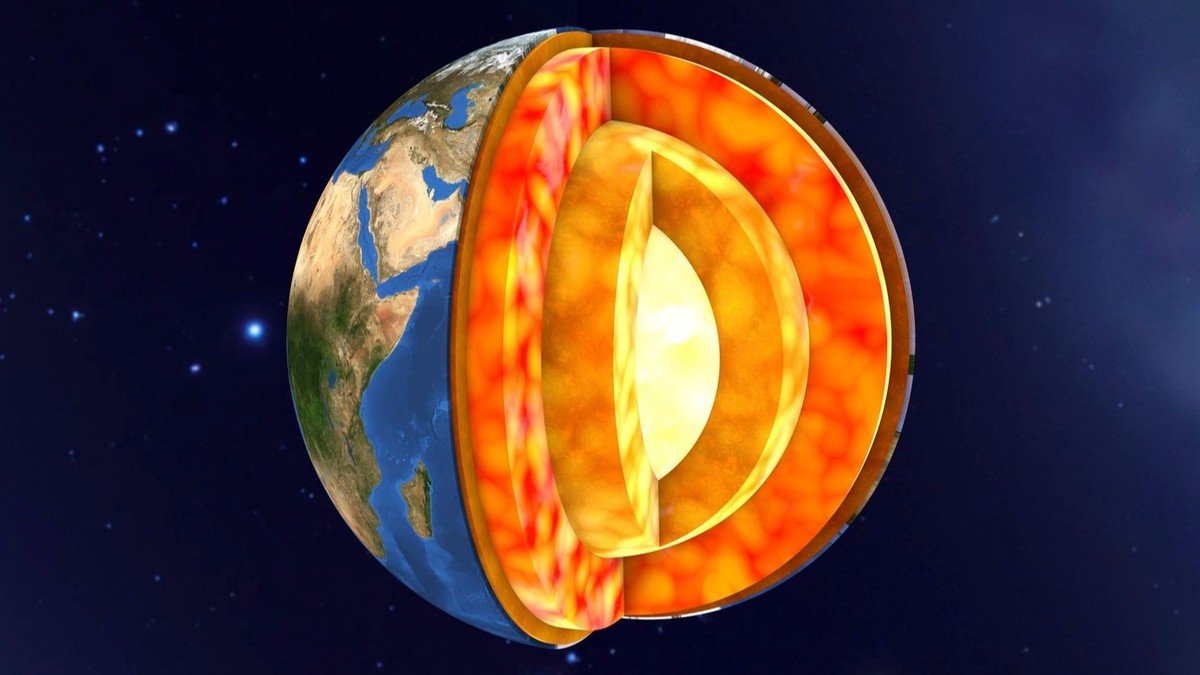



:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/irishtimes/M552H3LB3JDXXCO4C4W2ZQT56Y.jpg)





