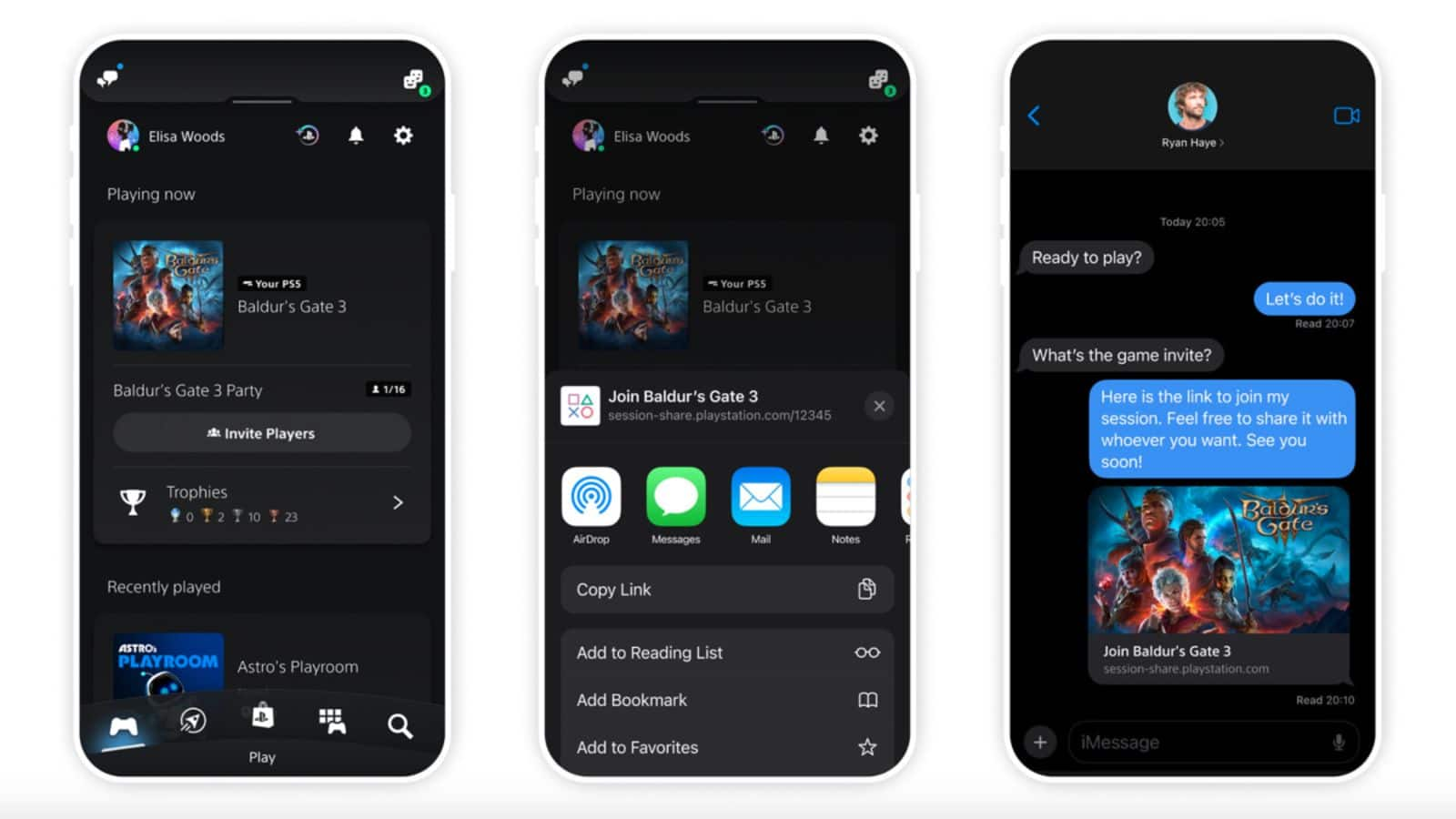1712037264
2024-04-02 03:30:00
彼 国立奴隷博物館、スリナム(南米)とオランダ領アンティル(カリブ海)のオランダの旧植民地に住むアフリカ人コミュニティの子孫による待望のプロジェクトが具体化しつつある。 政府とアムステルダム市議会からの資金提供を受けて、この新しいセンターは、17 世紀から 19 世紀にかけての奴隷搾取が国の経済的および社会的発展にとって決定的なものであったことを示すことを目的としています。 永続的な場所として構想、そのデザインは今年2月に発表され、奴隷の歴史とアイデンティティが奴隷船の到着よりずっと前から始まっていたことも強調することになる。 何十年にもわたる要望を経て、開業は2030年を予定している。
「私たちはこの博物館のために60年間戦ってきました。国家として共に前進するためには奴隷制度に対処しなければなりません」と、元社会民主党議員で、博物館の3人の専門家のうちの1人であるジョン・リアダム氏は電話で語る。プロジェクトを準備しました。 この70年間、カリブ海とスリナムのアフリカ人コミュニティ(そのメンバーの多くはオランダ領に住んでいます)の声がオランダで絶えず聞かれ、そのような機関を求めてきました。 「皆さんの先祖が苦しんだカリブ海の6つの島々は、現在ではオランダ王国の一部であることを心に留めておいてください」とリールダム氏は思い起こす。 “そして 植民地主義は、双方の関係をある意味で特徴付け続けている”。 アルバと同じく独立国の地位にあるキュラソー島とセント・マーチン島を指します。 そして、オランダの特別自治体とみなされるボネール島、セント・ユースタティウス島、サバ島へ。
教育と博物館学の専門家であるペギー・ブランドンは、博物館計画を担当するトリオの一員であり、奴隷の子孫は「自分たちの国でもある国に帰属しているという感覚を持っていなかった」と断言する。 彼らは 1950 年代以来何が起こったのかを認識するよう求め続け、小規模な一時的な展示会を組織し始めました。 アムステルダム市議会は2017年に常設機関の設置にゴーサインを出し、2019年には政府も参加した。 2021年、フェムケ・ハルセマ市長は奴隷制度において首都が果たした役割とそこから恩恵を受けていた富について謝罪した。 その後、ユトレヒト、ロッテルダム、ハーグ、ハーレムなどの他の都市や、オランダ国立銀行やABNアムロ銀行などの機関も同様の取り組みを行っています。
ブランドンの曽祖母はスリナム出身で、解放された奴隷の娘でした。彼女は現地の博物館に対する態度を確認するためにジョン・リアダムとともにカリブ海とスリナムを旅行しました。 「キュラソー島のアーカイブで1863年の文書を見つけました。 [fecha de la abolición por parte holandesa] そこでは奴隷たちは今は自由であると告げられたが、以前の状態と同じ沈黙と従順が彼らに期待されていた。」 彼らは最終的に合計 5,000 人と話をし、彼らが説明した内容について話しました。 今も子孫を囲む沈黙の輪。 「彼らは、私たちが白人男性の罪悪感の一部であるかどうかを知りたがっていました。 つまり、博物館を開きたいと思ったら、それだけです」とリールダム氏は言います。
もう一つの有名なオランダ植民地であるインドネシア人の子孫からの圧力はそれほど強くはありませんが、その過去も博物館で取り上げられます。 ブランドン氏によれば、「世界の両端の間のつながり」を見る必要があり、その例を挙げています。 これは、損失を補うためにカリブ海とスリナムの解放奴隷の所有者に支払われるお金です。 「これらの金額はインドネシア国民から強制的に搾り取られたものであり、平均的なオランダ人はそのことを知りません。」

オランダの首都にある自由大学(自由大学)の歴史家ペピン・ブランドン教授(世界史)にとって、他のテーマもインドネシアの植民地時代の記憶に役割を果たしてきた。 特に、独立戦争(1945年から1949年)中にオランダ人によって犯された戦争犯罪。 「さらに、19世紀末から20世紀にかけて、奴隷制度の廃止は、まだ奴隷がいたインドネシア地域を植民地化する口実として利用されました」と彼は言う。 そしてそれが反植民地主義の視点を曇らせている。なぜなら「反奴隷制の言説は最終段階の植民地化者の主張だったからである」。
認識の変化
オランダの博物館はコレクションの中で奴隷制について言及していますが、 アムステルダム国立美術館が2021年に開催する展覧会アムステルダムから、後続のペースを設定しました。 17 世紀と 18 世紀の歴史論争において、奴隷貿易は周縁部であったため、認識は時間の経過とともに変化しました。 19世紀には、一般的な道徳はそれに参加する人々を拒否しましたが、「経済的および社会的発展にとってそれはまだ重要とは考えられていませんでした」と歴史家のブランドンは述べています。 彼は、それが「征服者ではなく商人の国の自己認識には当てはまらなかった」と述べています。 寛容でリベラル。」 したがって、植民地時代のプランテーションにおける人身売買とその後のくびきは、「他のページから切り離せるかのように、黒いページ」として表現されました。 彼は 2013 年の変化の瞬間をこう語ります。 スリナムとカリブ海の奴隷制度廃止150周年を記念。 オラニエ公ウィリアム王は、ヨーロッパの総交通量の約5%がアフリカからアメリカに貿易されたことを理由に「後悔と悔い改め」を表明した。 10年後の2023年には、 主権者は国家元首として許しを求めた。 2022年にも彼は同じことをした マルク・ルッテ首相。 「しかし、2013年以降、奴隷制がオランダの富裕化の代償となったという事実を議論は避けられなくなった。」
また、植民地ビジネスを支配していた2社の株式を保有していた多くの一族の資産間の直接的なつながりについても、何年も言及されなかった。 彼らは東インド会社と西インド会社でした。 最初は南アフリカとアジア、現在のインドネシアで行われ、歴史的な推定では60万人から100万人以上の人身売買が行われたとされています。 もう1つはスリナム、ブラジル、カリブ海で交渉し、コーヒー、タバコ、砂糖、綿花、カカオのプランテーションで60万人近くの人間を制圧した。

植民地時代の過去を持つ各国は、それを異なる方法で扱っています。 他の場所ではどうでしたか? 「例えばイギリスにとって、奴隷制度は集団の記憶に残る画期的な出来事です。なぜなら、奴隷制は廃止における大英帝国の輝かしい役割に焦点を当てているからです」とペピン・ブランドンは言う。 後で思い出すために:「真実を言えば、18世紀には彼らは世界最大の奴隷密売業者でした。」 オランダの日付は、2 つの重要な瞬間を示しています。 廃止は 1863 年に行われ、時系列的には 2023 年にケティ コティ (壊れた鎖) と呼ばれる式典が行われて 160 周年を迎えました。 しかし、1863年から1873年の間、解放された奴隷は、元の主人が奴隷を購入する際に行った投資を失わないように、悲惨な賃金で働かされることを強制されました。 そのため、鎖は 150 年前の 1873 年に決定的に切れたと考えられています。
国立奴隷博物館の提案には、アムステルダムの港地区に9,000平方メートルの建物が含まれている。 ペギー・ブランドン氏によれば、それは「複数の視点を提示し、視点や知識を共有する場所」になるという。 展示される品物は奴隷に関連するものだけでなく、ディアスポラのメンバーによって制作された現代アーティストの作品も展示されます。 「展示されているものは、民族誌的な観点からだけではなく、芸術として見られるべきです」と彼女は警告する。 「多くの関心が寄せられており、私たちはワシントンにある国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館からインスピレーションを受けました」とリールダム氏は言います。 「オランダ国民の一部は過去について非現実的な見方をしており、この種の情報が国家イメージを損なうと信じている」と歴史家は指摘する。 しかし、3 人全員が、博物館に対する公式のコミットメントは堅固であることに同意しています。
あなたと一緒に過ごすあらゆる文化がここであなたを待っています。
バベリア
週刊ニュースレターで最高の批評家が分析した文学ニュース
続きを読むには購読してください
無制限に読む
_
#オランダは博物館で植民地時代の過去を振り返り奴隷制のおかげで発展したことを認識する #文化